こんにちは。
ソフトウェアエンジニアの私が、最近読んで感銘を受けた書籍をご紹介します。
こちらの書籍です。
世界一流エンジニアの思考法
書籍紹介
著者はマイクロソフトでエンジニアとして働かれている方で、
米国のビッグテックでの業務経験から一流のエンジニアに共通する思考法や生活習慣などを執筆されています。
エンジニアとしての適正があまりなかったと自称する著者が、実際に世界トップレベルのエンジニアに囲まれる環境の中で気づきを得て実践し、効果を得たティップスが多く書かれています。
特にこれからキャリアを築いていくような若いエンジニアが悶々と抱えていそうな悩みを著者の方も持たれていて、それらを解決、解消する指針を示してくれるので
「こんな悩み自分も抱えているんだよね!」と共感しやすく、それが故にすぐにでも仕事で実践できそうな内容ばかりだったのが
読んでいてすごくバリューを感じた書籍でした!
まさに霞が勝った前途の道がパッとひらけたような感覚になります。
初級/中級関係なく、エンジニアとしてスキルアップしたい、生産性を上げたい、ひいては仕事をもっとエンジョイできるようになりたい、と考えている方は是非一読してみることをオススメします!
下では、私が特に感銘を受けたトピックを3つほど挙げています。
「コントロールできている感」を身につける
私は今の仕事についてもう6年以上経ちますが、特に途中でリタイアすることもなく
今まで仕事は一応こなしてはきました。
しかし、
どうにも各タスクや事業の方針に対してその本質、骨の髄まで本当の意味で理解し切れておらず
それゆえに関わっているタスクを自分が握っている、という感覚がいまいち芽生えない
ということが数年間ありました。
著者はこれを、基礎的なベースの知識を真に身につけていないからだと言います。
そしてそれを身につけるには、一旦時間をかけて、ステップを飛ばすことなく1から丁寧に時間をかけて身につけるという過程が大事だと説明します。
確かに仕事上では個人の知識習得のためにはそれほど時間をかけられる余裕はなく、
タスクを遂行する上で必要な事項だけをさらっとインプットし
その知識が本当の意味で自分に根付いているかを吟味することもなく次のタスクに移行する
ということが非常に良くあります。
こういったプロセスを繰り返していると、
ふと振り返った時に自分の知識はしっかりと基礎から建っているものではなく
地盤がゆるゆるになっているも同然だということに気付かされるのですね。
私もこういった経験が幾度となくありました。
確固としたベースの知識を持っていないと
仕事全般に対する推測、考察などの段階でも限界まで深ぼった思考をすることができず
いずれパフォーマンスに大きく弊害が出てしまいます。
そうならないためにも、基礎の知識は絶対に固めておく必要があるんですね。
しかし持っていない知識の理解というものは時間のかかるものです。
日々の仕事に追われている中でこなすのはなかなか簡単ではありません。
そこで著者が主張するように
生活の中のどこかでしっかり時間をとって、丁寧にじっくりとベースを身につける、という行動をとることが大切になってくる
ということです。
そうして知識のベースを盤石なものにすることで
仕事へのアプローチも一段レベルの高いものにでき、著者のいう
「仕事をコントロールできている感」
につながるのですね。
優先順位はトップ1つだけでOK!
仕事をしていると日々タスクは積み重なっていきますが、
それらの優先順位をつけて順位の高いものからこなしていくというフローはほとんどの企業で行なっていることだと思います。
私たち日本人がよくやるやり方では
1位、2位、3位、・・・と現状のタスク全てに対して順位づけしていき、上位から手をつけていきがちですが
著者によると米国では
数あるタスクの中から最も重要な1位タスクのみ厳選し、他タスクは一旦全無視してピックアップしたもののみに集中して取り組む
というやり方が主流だそうです。
日本人式のやり方だと1位のタスクを進行していても、
その後に控えている2位以下のタスクたちがどうしても頭の片隅に残ってしまうので
集中力という意味で1位タスクに対するパフォーマンスがどうしても落ちてしまいます。
さらに言えば、日々積み上がるタスクの中で本当に本当に重要なタスクなどそうそうありません。
大抵は着手しなくてもなんとかなるようなものばかりです。
それらに気を取られて一番大切なタスクへの取り組みが疎かになるくらいなら
一番のものだけをピックアップし、それに全力で取り組む方が最終的な事業に対するインパクトが大きいという考え方ですね。
タスク管理のフレームワークとしてKPTを実践していたりする職場も多いですが
Problem(課題)が溜まりに溜まってどれから手をつけて良いか分からない、というケースはよく見かけます。
なんとか優先順位をつけてみてもProblemの数自体が減るわけではないので
依然としてスッキリしないというのも起こりがちです。
そんな時は思い切って、一番重要なProblem以外はバッサリ切り捨ててしまう
ということが時には大切ということですね。

マルチタスクは厳禁!
これは昨今、巷で折りに触れて話題になることですが
マルチタスクというのは脳のパフォーマンス的には非常に効率の悪いもののようです。
人は並列思考をしているとどうしても脳の働きが鈍り
洞察力、推察力などの思考が浅くなってしまうようですね。

ただ現実の仕事では四方八方から常にいろいろな問い合わせが飛んできたり
度重なる会議で自分のタスクに集中できず
複数の業務を同時並行でこなす必要があることがほとんどだと思います。
こういった状況下にいるとき、マルチタスク的な脳の使い方を極力回避し
思考力をできるだけ落とさないようにするにはどうすれば良いか?
という疑問ですが
「今この瞬間に行なっているタスクだけに集中する」
というのが解です。
例えば
会議、開発、インシデント対応といった業務が入り乱れて予定に組まれていたとしても
会議の時間はその会議のことだけを考える。
開発をしている間は開発のことだけを考える。
インシデント対応の時間はインシデント対応のことだけを考える。
といった具合に、脳を現行タスクに一点集中させることで
複数のタスクを抱えていても、それをマルチタスクで進行しているのではなく
シングルタスクを次々に切り替えながら進行している形になり
マルチタスク特有の脳の衰えを極力防ぐことができる、というわけです。
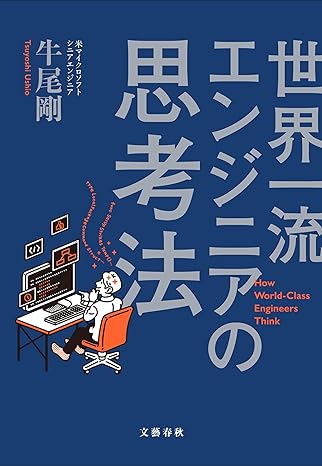


コメント